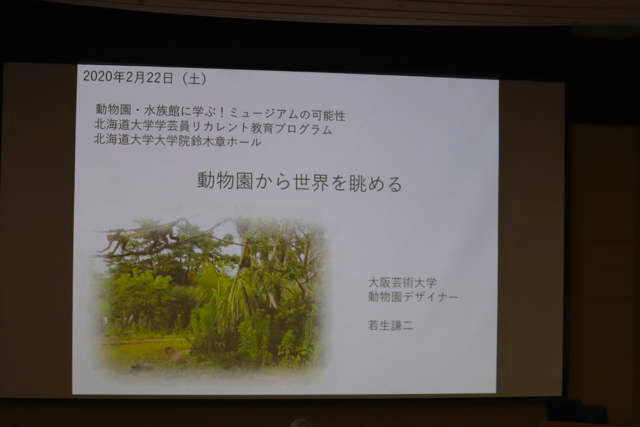動物園・水族館に学ぶ!ミュージアムの可能性
動物園・水族館に学ぶ!ミュージアムの可能性
峰岸 雅俊
北海道大学学芸員リカレント教育プログラムの特別レクチャー+クロストークとして「動物園・水族館に学ぶ!ミュージアムの可能性」が開催されました。
はじめに、大阪芸術大学教授の若生謙二氏から、動物園におけるランドスケープについて解説していただきました。また、野生動物の生息環境を動物園内に再現することにより、そこに住む人間と動物の関係性や地域環境を展示した例として、「熊本市動植物園」のニホンザルの展示を紹介していただきました。
続いて、関西大学教授の溝井裕一氏から、これからの水族館は、大型種・珍種を集めた巨大な水族館やショー中心の水族館ではなく、飼育点数を減らし、動物福祉に注力するとともに、「モントレーベイ水族館」や「アクアマリンふくしま」などをモデルに、地域の生態系を再現して美しく展示する水族館が、地域住民や海外観光客からの支持を得るのではないかとの考えが示されました。
北海道大学大学院工学研究院助教の平輝氏を交えたクロストークでは、札幌市環境局参与の小菅正夫氏をはじめとして、来場者との意見交換も行われました。「動物園や水族館、博物館等の機能を収斂して、自然と人の共生を多様な形で展示できないか」、「これからのミュージアムは、地域の特性を前面に出した展示が求められている」など、動物園や水族館にとどまらないミュージアム全般に関する議論は、示唆に富んだ内容となりました。
本プログラムの受講生・聴講生の多くは、美術館や歴史系博物館などの人文系ミュージアムに所属しています。受講生・聴講生にとって、専門の分野ではない動物園や水族館などの自然系ミュージアムの取組を学ぶことは、展示の手法だけではなく、今後のミュージアムの在り方についても考える契機になったのではないでしょうか。
クロストークを終えて
座談会参加者
- 門間 仁史 氏(北海道立旭川美術館主任学芸員)
- 亀丸 由紀子 氏(北海道博物館学芸員)
- 聞き手/今村 信隆 特任准教授
 (今村信隆特任准教授)
(今村信隆特任准教授)
今回は、クロストークの司会を務めてくださり、ありがとうございました。まずは、終わってみての率直なご感想をお聞かせください。
(門間仁史氏)
お声がけいただき、聞き手として、微力ながら参加させていただきました。学芸リカプロの事務局側にも大いに助けられながら、準備を進めたという感じです。
職業柄、様々な場面で司会役や聞き手を務めることも少なくありませんが、今回は独特の難しさもありました。
(今村)
難しさと言いますと?
 (門間)
(門間)
まず、動物園・水族館と美術館・博物館という館種の違いに由来する難しさです。自分たちにとっては当たり前だと感じていることでも、館種が違うと、想像さえ及ばないことが多々あります。「展示」や「保存」といった基本的なワードでも、お互いが用いているニュアンスに差がないかどうか、来場者にそのニュアンスが正確に伝わっているかどうか、といった配慮が必要でした。
もうひとつは、立場の違いからくる難しさです。聞き手である私たちは現場に立つ学芸員ですが、若生先生と溝井先生は大学に籍を置く研究者です。そのあたりの、目指している地点の違い、直面している課題の違いが、トークとしてマイナスにならないよう、違いから有益な対話が生まれるよう、気をつけました。
最後に、クロストークという形式、あるいは聞き手という役割の難しさです。若生先生と溝井先生がそれぞれ基調講演を行ってくださったので、議論の前提を共有することができました。ただ、そうした動物園・水族館の事例に、聞き手である私たちは美術館や博物館といった人文系ミュージアムの事例をぶつけていかなくてはならなかったわけです。実際には、私たちの側の事例を充分に丁寧に紹介することが、時間的にも困難であったように感じています。
(今村)
とはいえ、そうした困難にもかかわらず、クロストークは概ね好評でした。若生先生からは、クロストークは「刺激的なものであった」、溝井先生からは「大いに盛り上がった」という感想をいただいています。また、来場者のアンケートには、「ジャズの演奏のように」スリリングだった、という声もありました。
(門間)
そうであれば、ありがたいことです。もしうまくいったのであれば、私としては、その要因をふたつ挙げておきたいと思います。
ひとつは、この手のトークの鍵を握るのは、何と言っても事前の信頼関係の構築だということです。本番の直前に登壇者が顔をそろえ、ランチミーティングを行いましたが、その場ですでに議論が白熱していました。若生先生、溝井先生、そしてコメンテーターの平先生。登壇者同士は初めて顔をあわせる場面でしたが、すでに事務局を中心に、良い関係性を築くことができていたのだと思います。
もうひとつは、登壇者の人選。私も驚いたのですが、若生先生と溝井先生のお話は、異なる出発点から、異なる経路を通って、しかし同じような結論に至るというものでした。かつての「支配」の表象としての動物園・水族館から、「共生」の場としての動物園・水族館へという流れを、溝井先生は歴史的な必然として論じ、若生先生は実践者として論じていた。また、登場してくるキーワードのなかにも共通する部分が多かった。こうしたことが、クロストークでの活発な議論を生んだのだと考えています。
(今村)
亀丸さんは、全体を通して、いかがだったでしょうか。
 (亀丸由紀子氏)
(亀丸由紀子氏)
私は、北海道博物館で勤務をはじめてからまだそれほど年月が経っていません。イベントの司会などの経験も乏しく、その意味では、大変良い経験になりました。周りの皆さん、特に門間さんに議論を引っ張ってもらったという印象です。
(門間)
いえ、亀丸さんもトークでは堂々と感想や質問を述べられていました。私のような、すでに中堅といった立場の学芸員から言えば、若い世代の学芸員がこのようなかたちで育ってきていることは、頼もしく思います。
(亀丸)
先ほどの、議論が盛り上がったという点について、私は会場に集まってくださった皆さんの多様さも、要因だと考えました。
会場には、人文系ミュージアムの学芸員や関係者に加えて、北海道内の動物園関係者、理系の学生、歴史学を学ぶ学生、小中学校の教諭など、多彩な顔ぶれが集まってくださっていたようです。
トークの後半で質疑応答を行いましたが、質問はどれも興味深いものばかりでした。動物園で勤務する専門家から動物園のキャプションやサインのデザインに関する質問が飛んだかと思えば、歴史学を学ぶ学生から「記憶」の保存と継承に関する質問が飛ぶ。また、コメンテーターとして登壇されていた工学研究院の平先生も、人文系の研究者とは別の視点から、発言をしてくださっていました。
ジャンル横断的な、刺激的なディスカッションになったのではないかと思います。
(門間)
確かに、ジャンル横断的なディスカッションが、若生先生、溝井先生からも次々と発言が飛び出す一因だったのかもしれません。両先生が、別の発言者に触発されるかたちでさらに発言を重ねていく、という場面が何度かみられました。
加えて、両先生のタイプの違いも、印象的でした。若生先生は、現場に立つ実践者に欠かせない信念を持ち、物事を具体的に動かしていくエネルギーに満ちていました。対する溝井先生には、歴史学者ならではの軽やかさ、しなやかさがあり、どのような話題も拾ってくださるという安心感がありました。
(今村)
最後に、トークを通じてみえてきたミュージアムの課題について、教えてください。
(門間)
私の場合、どうしても美術館に当てはめて考えてしまうのですが。
両先生のお話によって、博物館が「支配」から「共生」の場へ変容する様が浮き彫りになりましたが、これは内面的に言えば「欲望」から、若生先生の言葉を借りれば「福祉」へと、博物館の理想が変化したようにも見えます。例えばコレクションの形成にしても、かつては重要な資料を可能な限り収集することが理想とされていたのに対し、今では既存の資料を良好な状態に保つためにコレクションを増やさない、さらには数を減らすことまで視野に入れた議論がなされています。これは単に収蔵スペースの物理的な限界といった問題に帰結する話ではなく、博物館の持続可能性と、なにより資料への「福祉」のありようを探る議論であるように思えます。動物園や水族館は、生命を扱う博物館であるためか、いち早く「福祉」の重要性に気づいたのでしょう。まだ美術館の分野では充分に理論化されていない部分だと思いますので、「福祉」の示唆を得られたのは大きな成果でした。美術館の「福祉」とは何か、考えてみたいですね。
(亀丸)
私も、先ほど門間さんが言われていたとおり、お二人の先生から「共にある場(共生)」としての博物館というお話がでたことがとても印象的でした。昨今話題となっている博物館と地域との”連携‟や”協同”もそうですが、何より、2020年4月には白老町に誕生する国立アイヌ民族博物館が”民族共生象徴空間”という名前でオープンします。そうしたことからも、ミュージアムのあり方や存在意義といったことについて、社会や世界が一丸となって考えてゆく、そんな時代の到来を強く感じました。
会場からも、「その時代時代の世相を映し出す装置としての博物館」というお話がありましたが、当日、あの会場でも「博物館と共生」について様々な立場から議論や想いを交わしたことで、間違いなくミュージアムの歴史の中に身を置いているような、そんな感情さえ覚えました。
各種のミュージアム関係者が一堂に会し、ミュージアム全体の課題に向き合ったこと自体が、「共生」への大きな一歩であったと強く感じました。