8月5日~7日の3日間、Hokkaido Summer Institute 2024 / Hokkaidoサマー・インスティテュート2024開講リカレント科目「侵略的外来種防除専門家養成講座」(Training course for specialists in invasive alien species management)をハイブリッド形式で開講しました。
文学部・文学院では、池田透名誉教授(2023年度まで地域学研究室教授)が責任教員となり、HSIが開始された2017年以降、継続してニュージーランドLandcare Research (Wildlife Ecology & Management)から研究者を招へいし、学部生向けの侵入生態学についての基礎知識を学ぶ科目「Social Ecology: Principles of Invasion Ecology / 社会生態学: 侵入生態学原論」や、大学院生向けに最先端の侵略的外来種対策・管理に関する科目「Regional Sciences (Lecture) : General Theory of Invasive Alien Species Management / 地域科学特殊講義:侵略的外来種管理学総論」を英語で開講してきました。今年は責任教員だった池田透先生が招へい講師となり、社会人向けに日本語で侵略的外来種の防除に関する実践的専門家の養成を目指すリカレント科目を開講しました。
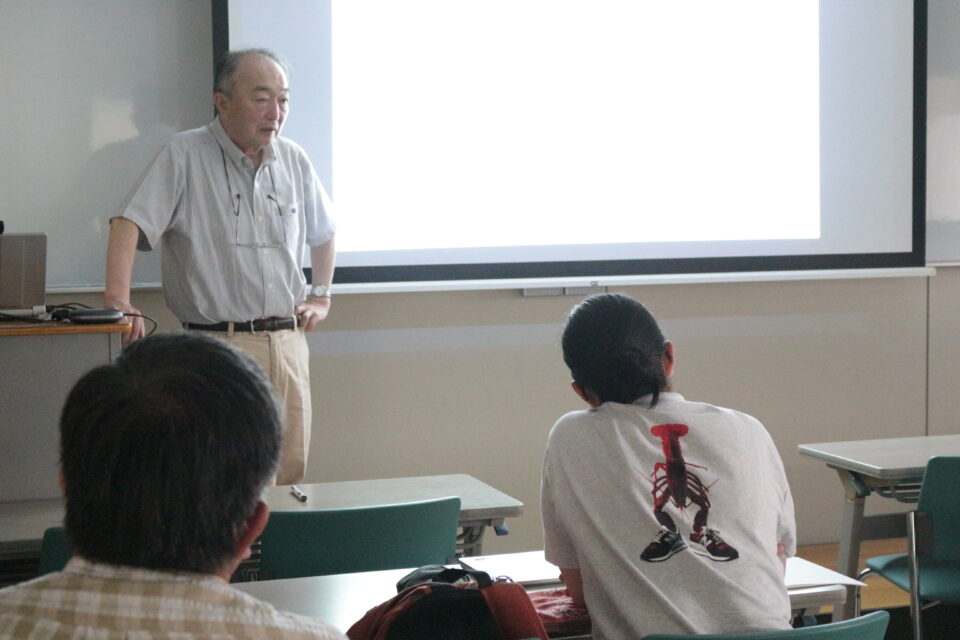
“過去50年の間、人類史上かつてない速度で地球全体の自然が変化している。侵略的外来種は、土地と海の利用の変化、生物の直接採取、気候変動、汚染とともに、生物多様性に直接的影響を与える要因として注目され、世界的に対策が必要となっている。しかし、日本では、組織的に外来種問題を扱う大学が少なく、対策を担う自治体職員やNPO等の職員に対策に必要な基本的理論や対策技術・戦略等の情報が共有されていないという問題がある。”(本科目のアブストラクトより)
そこで、本科目は、包括的な外来種問題のリカレント教育を目的に、主に現役で外来種問題に携わっている社会人を対象に実施することで、侵略的外来種の防除に関する実践的専門家の養成を目指しました。講義には、2023年9月4日に【生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム(IPBES)】から全世界に向け一斉に公表された「侵略的外来種に関するテーマ別評価報告書 政策決定者向け要約」と、その背景となる6章からなる報告書全体の内容を整理したテキストが用いられ、参考図書として『日本の外来哺乳類 : 管理戦略と生態系保全』東京大学出版会2011と『外来種ハンドブック 日本生態学会編』地人書館2002が指定されました。
3日間の集中講義は毎朝1限から始まり、夕方の5限まで続き、受講生にとっては全15コマの盛りだくさんの内容です。初回は講義に先立ち、講師の池田先生から自己紹介があり、本科目の開講目的である「外来種問題を自分たちの生活と密接な関係のある問題として捉え、適切な防除の方向性を考え、技術・戦略を身に着ける」ために、侵略的外来種がどのように発生するのか?というプロセスを理解することからスタートしました。
講義はまず外来種問題に関する序論から始まり、基本的定義の整理、侵略的外来種の動向と現状、侵略的的外来種に影響を与える変化要因、自然及び人間社会への影響、侵略的外来種の管理、ガバナンスと政策オプション、効果的・効率的な防除手法と戦略についての講義が続きました。ここで受講生は、最初に知っておくべきこととして侵略的外来種が問題になるはるか以前の時代に遡り、どのような動物や植物が、どこからどこに、どうやって移動し、移動した先で定住したのか、あるいは定住できなかったのか、などの歴史的な経緯について学びます。そういった背景をベースに、今度はこの半世紀の間に顕在化した侵略的外来種問題について生態系や社会、経済に損害を与える仕組みやその複雑な要因、さらには侵略的外来種管理に必要な法制度や政策オプションについて理解を深めます。そのうえで、本科目の後半では効果的なコントロール戦略・技術・ツールなどを考慮しながらリスク評価を実施する方法を身に着け、適切な防除策を構築するためスキルを習得して全15回の講義を終えました。
さらに、講義では世界機関の政策と現在までの日本の状況に加えて、海外の事例として侵略的外来種対策の最先端をいくニュージーランドで実践されている対策やその効果、今後の課題についても豊富な画像とともに紹介されました。同じ島国でも日本とは事情の異なるニュージーランドの成功例と失敗例を学びながら、これからの日本でどのように参考にできるのか、考えました。
集中講義期間中は毎日、その日の最後の講義終了後に授業で使用したテキストやオンデマンド教材がmoodle上で共有されました。参加者は資料を活用しながら復習をすることで、講義内容をより深く理解することができる仕組みです。本科目は日本語で実施するリカレント科目のため、学生は単位が付与されませんが社会人受講生にはレポート提出後に合否判定があり合格するとデジタルバッジが付与されました。
今年初めて開講した本科目ですが、メインターゲットだった社会人の参加者も多く他学部から参加する学生と一緒に連日朝から夕方までの3日間にわたる集中講義で侵略的外来種の防除に関する実践的専門家として必要な基本的理論や対策技術・戦略等の情報を学びました。
日本全国で外来種対策を担う自治体職員やNPO等の職員を対象に、共有包括的な外来種問題のリカレント教育を実施、侵略的外来種の防除に関する実践的専門家の養成を目指す本科目は、来年夏も8月開講を予定しています。








