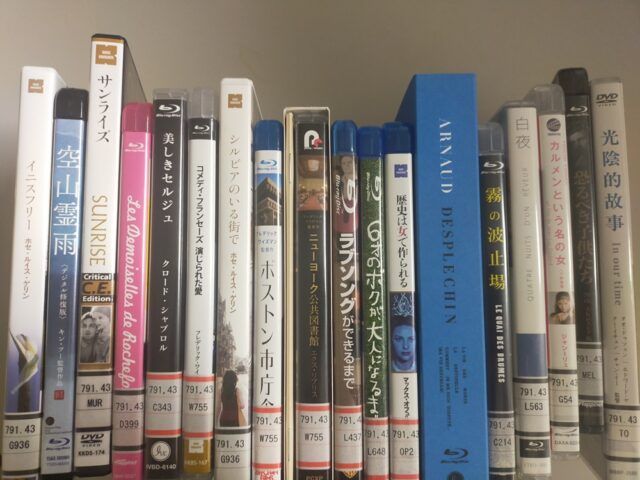プロフィール
- 研究内容
映画論、表象論、中国映画・文学論
- 研究分野
- 映像表象論
- キーワード
- 未来、無理数的世界
- 文学研究院 所属部門/分野/研究室
- 人文学部門/表現文化論分野/映像・現代文化論研究室
- 文学院 担当専攻/講座/研究室
- 人文学専攻/表現文化論講座/映像・現代文化論研究室
- 文学部 担当コース/研究室
- 人文科学科/言語・文学コース/映像・現代文化論研究室
- 連絡先
研究室: 422
TEL: 011-706-4020
Email: yingpang*let.hokudai.ac.jp
(*を半角@に変えて入力ください)研究生を希望される外国人留学生(日本在住者をふくむ)は、「研究生出願要項【外国人留学生】」に従って、定められた期間に応募してください。教員に直接メールを送信しても返信はありません。- 関連リンク
Lab.letters



スクリーンを走る一秒間二四コマ
人生も映画のように走ればよい
「物質にせよ精神にせよ、実在は、われわれにとって、不断の生成としてあらわれる。……実在は、決して、できあがった何ものかではない」(ベルクソン)。
「神は計算して世界をつくるという話がまったく本当だとしても、その計算はけっしてきちんと割り切れるようになるものではない。計算の結果に残るそのような割り切れなさ、そのような解消されない不等性、それこそが、世界の条件をなしているのである」(ドゥルーズ)。「予定調和」に基づく古典的映画と異なり、真の現代的映画は、「出来損ない」の相貌を帯びつつ世界や人生を捉える。私もそれに似たようなアプローチを試みているところです。
偏りを排した幅広い教養を糧に
新しい変化を恐れない研究者へ
何を専門としているかと関係なく、人文学にまつわる幅広い知識を身につけてほしいと思っています。修士・博士論文では、先行研究をなぞるだけでなく、必ず新しい「何か」をあなた自身が書かなければなりません。その「何か」を見い出す際にも、映画以外の広い教養がおおいに役立ってくれます。映像・表現文化論を含む人文学は、つねに新しい変化が待たれる分野です。現状に満足せず先に進むことを恐れない研究姿勢は、皆さんの人間としての成長をも後押ししてくれることでしょう。広がりと新しい発見がつねに授業のキーワードになっています。
メッセージ
『気違いピエロ』の冒頭でベルモンドが朗読するエリー・フォールのベラスケス論の一節はこのように始まります、「ベラスケスは五十歳をすぎてからはもはや、形のはっきりしたものは少しも描こうとしなかった。彼は大気と黄昏とともに対象のまわりをさまよい、背景の陰影と透明さのなかに、彼の沈黙の交響楽の見えない中心をなしている、痙攣するかのような色彩をとらえていた」と。形態と形態の間にあるもの、大気、塵、陰影、波動といったようなものを捉えてみる、このことに人文学の素晴らしい出会いがあるはずです。
研究活動
主要業績
- 【著書】『徳勒茲, 或喜悦的電影学』山西出版伝媒集団・三晋出版社、2025年
- 【著書】『中国映画のみかた』【編著】大修館書店、2010年、pp.1-307。
- 【著書】『中日影像文化的地平線』【共編著】、中国電影出版社、2009年、pp.1-225。
- 【論文】「オーソン・ウェルズ 人物論と〈視覚の建築〉」、『層―映像と表現』第12号、2020年、pp.21-47。
- 【論文】「ゴダール、アクション、未来(1)」、『層―映像と表現』第8号、ゆまに書房、2015年、pp.83-108。
- 【論文】“Body/Space and Affirmation/Negation in the Films of Lou Ye and Wong Kar-Wai”, in Deleuze and Asia (ed. Ronald Bogue, Hanping Chiu and Yu-lin Lee), Cambridge Scholars Publishing, 2014, pp.163-181.
- 【論文】「徳勒茲《電影2》読解:時間影像與結晶」、『電影芸術』、2010年第6号、pp.96-104。
- 【論文】「徳勒茲《電影1》中的“運動影像”」、『電影芸術』、2009年第4号、pp.112-118。
- 【論文】「張徹映画にみる運動」、応雄、『層―映像と表現』創刊号、2007年、pp.70-94。
- 【映画評】「ショットの倫理―三宅唱映画についての覚書」、「差異の恋愛学 今泉力哉映画研究ノート」、「「正しく傷つく」こと、正しく発語すること―『ドライブ・マイ・カー』について」(『層―映像と表現』第14~16号)、「『春江水暖~しゅんこうすだん』 長回しでかくれんぼ」(『キネマ旬報』、2021年2月下旬号)など。
所属学会
- 日本映像学会
教育活動
授業担当(文学院)
- 映像表象文化論特殊講義
- 映像表象文化論特別演習
授業担当(全学教育)
- 芸術と文学