プロフィール

- 研究内容
日本列島およびシベリア・ロシア極東の先史人類社会について、環境適応という視点から研究を行っています。特に後期更新世末から完新世前半の環境激変期における技術革新とその伝播、人類の行動的・社会的変化について研究を進めています。
- 研究分野
- 考古学、先史考古学、地考古学
- キーワード
- 狩猟採集社会、人類生態系、適応行動論、石器技術、遺跡形成過程
- 文学研究院 所属部門/分野/研究室
- 人文学部門/歴史学分野/考古学研究室
- 文学院 担当専攻/講座/研究室
- 人文学専攻/歴史学講座/考古学研究室
- 文学部 担当コース/研究室
- 人文科学科/歴史学・人類学コース/考古学研究室
- 連絡先
Email: dnatsuki*let.hokudai.ac.jp
(*を半角@に変えて入力ください)研究生を希望される外国人留学生(日本在住者をふくむ)は、「研究生出願要項【外国人留学生】」に従って、定められた期間に応募してください。教員に直接メールを送信しても返信はありません。- 関連リンク
Lab.letters
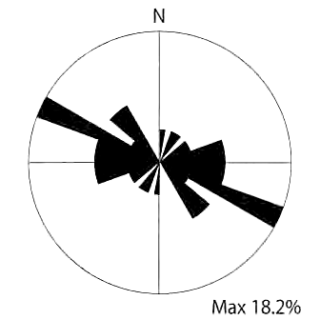


北海道の白地図に眠る
狩猟採集社会を明らかに
日本列島の人々の起源を考える上で北海道は大陸との関係性から非常に重要な位置を占めています。ところが意外にもその広さと人口密度の低さから考古学調査的には白地図の地域が多く残っています。新たな発見によって従来の定説を更新していく考古学者にとって、北海道の白地図はそのまま宝の地図のようなもの。その空白に挑む面白さに魅せられています。
私の関心は旧石器時代の狩猟採集民の人間行動を明らかにすることです。石器の集積を発見したときにそれは意図的にそこに捨てられたものなのか、使われた場所にそのまま放置されたものなのか。遺跡の地学的・空間的なデータ分析から当時の狩猟採集社会を立ち上らせようとしています。
多角的に揺さぶりをかけて
問題解決に導く発想力
考古学の対象は動植物や古環境あるいは人間社会など実に多様です。その対象に向かって古代土壌DNA解析や石器の使用痕分析などのさまざまな手法でアプローチしていくのが考古学研究者の腕の見せどころです。問題に対して論理を組み立て多角的に揺さぶりをかけていく発想力は、一社会人としても求められる要素です。ときには自説を手放し視点を改める勇気も、考古学から得られる大切な学びの一つです。北海道大学には北方の考古学を探究してきた長い歴史と稀少なコレクションがあり、札幌キャンパスからもいくつもの遺跡が発掘されています。従来の定説に疑問の余地は全くないのか。北海道から掘り起こす発見がその答えを照らしてくれます。
(聞き手・構成 佐藤優子)
メッセージ
考古学では、石器が利用され始めた約260万年前から現代まで、過去の人類活動にかかわるあらゆる物質資料を対象に歴史を研究することができます。考古学といえば石器や土器、金属器に関する研究が主流でしたが、方法自体の多様化や他分野との連携研究も進展してきており、動物考古学、植物考古学、民族誌考古学、遺伝子考古学、認知考古学などの分野が生まれてきました。考古学研究室には様々な専門の教員がおり、環境も整っていますので、みなさんが興味・関心のあるテーマをみつけ、研究を深めるお手伝いができると思います。私は旧石器~縄文時代・新石器時代の遺物を主に研究していますが、遺跡の層序学、遺跡形成過程、遺跡景観について科学的に理解するために地考古学(Geoarchaeology)の方法を用いた遺跡研究にも取り組んでいます。
考古学の醍醐味は何と言っても発掘調査です。考古学を学ぶうえでは避けては通れません。野外調査のため大変なことも多いですが、仲間たちと交流し、ともに汗を流しながら、楽しく実践的に考古学を学ぶことができます。本を読んで得た知識は忘れることもしばしばですが、体を使って経験したことはよく覚えているものです。考古学研究室の教員はそれぞれ調査フィールドをもっていますので、みなさんが多くの経験を積めるようにサポートしたいと思います。
研究活動
略歴
宮崎大宮高等学校卒、福岡大学人文学部卒、東京大学大学院人文社会系研究科修士課程・博士課程修了、博士(文学)。東京大学大学大学院人文社会系研究科附属北海文化研究常呂実習施設助教、同附属次世代人文学開発センター特任助教を経て、2025年より現職。
主要業績
- 夏木大吾 2016 「北海道における晩氷期人類の居住生活-吉井沢遺跡の事例から-」佐藤宏之・山田哲・出穂雅実編『晩氷期の人類社会』43-63頁、六一書房
- 夏木大吾 2020 「北海道における更新世・完新世移行期の土器出現と文化形成」『物質文化』100、39-49頁
- 夏木大吾編 2020 『日本列島北部における新石器型狩猟採集社会の形成過程-タチカルシュナイ遺跡M-I地点の研究-』、東京大学大学院人文社会系研究科附属常呂実習施設
- 夏木大吾編 2021 『北海道北見市吉井沢遺跡の研究(Ⅱ)』、東京大学大学院人文社会系研究科附属常呂実習施設
- Natsuki, D. 2022 Migration and adaptation of Jomon people during Pleistocene/Holocene transition period in Hokkaido, Japan, Quaternary International 608-609: 49-64.
- 夏木大吾・福田正宏・森久大 2025 「東北北部地域における弥生時代の食性復元」『東京大学考古学研究室紀要』38、31-45頁
所属学会
- 日本考古学協会
- 日本旧石器学会
- 日本第四紀学会
- 北海道考古学会
教育活動
授業担当(文学部)
- 考古学概論
- 考古学演習
授業担当(文学院)
- 考古学特殊講義
- 考古学特別演習
授業担当(全学教育)
- 歴史の視座
おすすめの本
- 『北辺の遺跡』藤本 強(教育社歴史新書―日本史〈17〉)
北海道独自の文化伝統・歴史を、環境とのかかわりあい、周辺地域との関係から読み解く、王道的な考古学本です。




